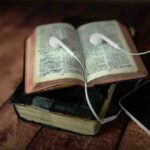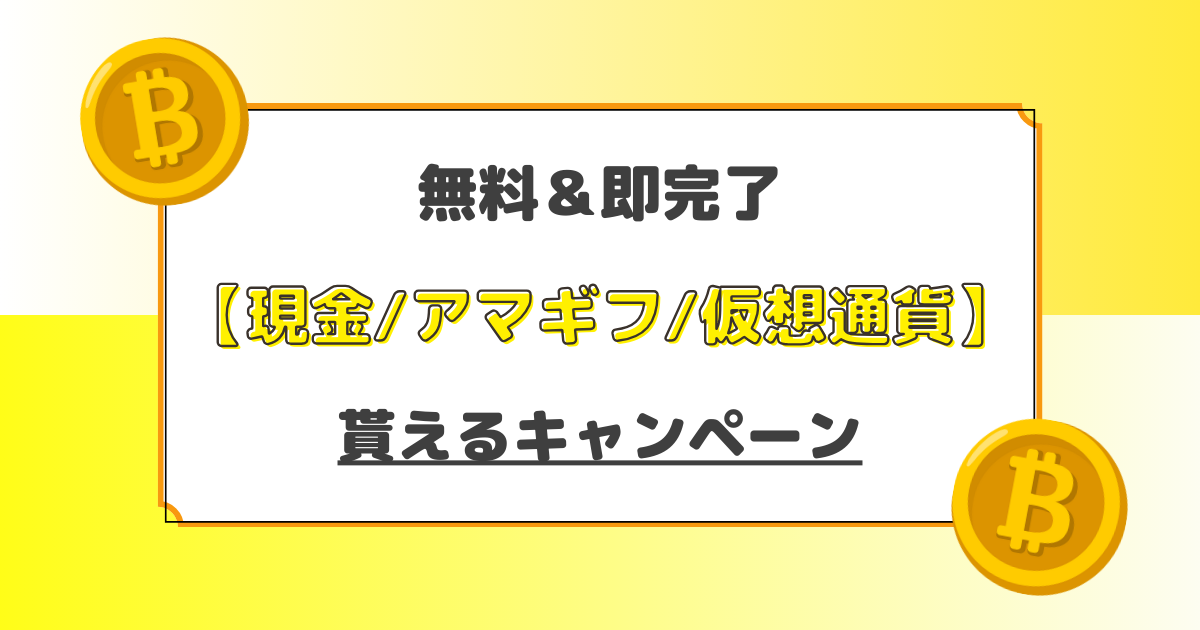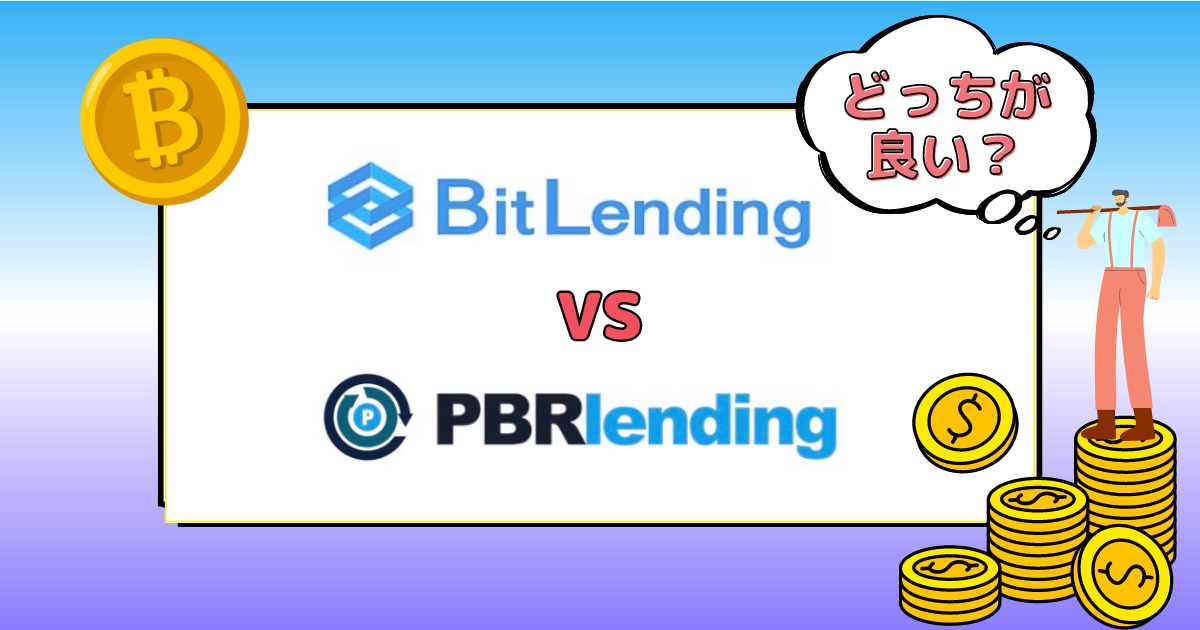どうも!ミチです。
つくづくiPadは本当に素晴らしいアイテムだと感じています。
iPadを使うようになって僕のライフスタイルは変わりました。
そこで今回は「iPadを使うようになって僕の生活が変わったこと」を紹介します。
こんな方へ👤
- モノを減らしたい
- 手軽になりたい
- 家での趣味を増やしたい、より楽しみたい
このように考えている方は特におすすめです。
今回の記事はiPad全般に当てはまりますが、その中でも「Apple Pencil 第2世代」が使える「iPad Air4以降」「iPad Pro」「iPad mini 6」が特に該当します。
ミニマリストという考え方に共感し不要なモノを手放したことで、より快適で充実した生活を送れるようになりました。
ミニマリストを目指す際、iPadが大活躍してくれて、今でもiPadを愛用しています。
そんなiPad大好きのミニマリストが「iPadを手にして変わったこと」を紹介していきます。
iPadを使えばモノが減り、手軽になり、生活が楽しくなる

僕はiPadを活用して
- モノを減らせた
- 手軽になれた
- 家での趣味がより充実して楽しめるようになった
それぞれ解説していきます。
モノを減らせる

ミニマリストを目指し、無駄なモノを減らす際に僕が重要視したこと
- スペースを取るモノ
- ゴミになりやすいモノ
- 失くしやすいモノ
- 壊れやすいモノ
- 時間を奪うモノ
これらのモノを優先的に手放すようにしました。その際にiPadが大活躍してくれました。
ノートやペンが不要になる

iPadは画面が大きいのでメモやスケッチを書く際に手軽に使用できます。
そして、iPadの相棒として「Apple Pencil」を用意すれば、ペンや消しゴムとして使用できます。
手が汚れたり、消しカスが出ることもありません。
またノートを取る際、写真や画像をノートに貼り、その上から書き込むことができるので、紙のノートよりも実用性が高いです。
紙の資料を手放せる

紙の資料の残念なところは
- 増える分だけ重くなり、かさばる
- 置いてあるだけで見栄えが悪くなる
- しわくちゃになる、破れる
- 失くす
- 環境に良くない
これらを考慮し、紙の資料を減らすように心がけました。
紙の資料を減らす上でiPadが活躍する2つの点は
- 紙の資料をPDF化できる
- PDF資料等に直接書き込める
それぞれ解説します。
①iPadのカメラから紙の資料をPDF等に電子化することが可能です。
紙の資料をもらった際、すぐに電子化してiPadに保管できるため、紙の資料は不要です。
②電子化されたPDF等に直接書き込むことができます。
パソコンでもPDF資料に書き込むことはできますがマウス操作のため字が汚くなります。しかしiPadなら紙と同じ感覚で書き込めます。
授業や会社でPDF等の資料をもらった際のメモ書きに最適です。
紙の書籍がなくなる
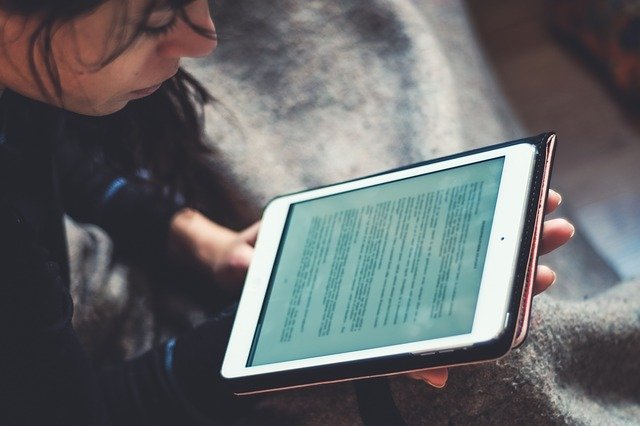
Kindleや楽天Koboのような電子書籍サービスをiPadでも利用できるため、紙の書籍を購入することがなくなりました。
電子書籍の良い点
- 何百何千冊の書籍を手軽に持ち運べる
- どこでも簡単に購入でき、すぐに読める
他にも電子書籍の良い点はあるので、他の章でも紹介します。
テレビを観る必要がなくなる

iPadを手にしてからはYouTubeなどの動画配信サービスをより快適に観られるのでテレビは不要になりました。
個人的にテレビは貴重な時間を奪ってしまうものだと感じます。テレビ番組は大衆向けに作成されているため、一人一人に与える情報の価値は低いです。また自分が観たいと思った番組もすぐに観ることができません。
その点、動画配信サービスは自分が観たいと思ったものをすぐに観ることができます。
パソコンの使用頻度を減らせる

IT関連の大学や会社に所属していない方、パソコンが苦手な方であれば、iPadで十分だと思います。
実際、僕もパソコンを使う場面としては、プログラミングやブログのように文字をたくさん入力する作業の時くらいで、それ以外のタスクはiPadで行っています。動画編集もiPadで十分可能です。
手軽になる

iPadが手軽で便利だと感じることを紹介します。
持ち運びが楽
ノートパソコンよりも軽く、カバンに入れてもかさばりません。またApple Pencil 2であれば、内蔵のマグネットにより直接iPadに装着できるので、ペンペースを持ち歩く必要もありません。
普段の持ち物をシンプルにしてくれます。
気軽に使用できる

パソコンを使う時は基本的に机が必要です。また起動するまでに時間がかかるため、使用する上での心理的なハードルは高いです。
しかしiPadはスマホと同じ感覚で使用できるため、そういった心理的なハードルを感じません。
またiPadでは、
ふとメモを取りたいとなった時にロック画面をApple Pencilでタッチすれば、メモアプリが自動で開くので、すぐにメモを取れます。
といった手軽さもあります。
電子書籍・資料の管理が容易

紙の書籍・資料を電子化するメリットとして、
- 場所をとらない
- 半永久的に保管できる
- 忘れない、失くさない
- 誰にも見られない
上記のことが挙がられます。それぞれ解説します。
1.場所をとらない
紙の本や資料は増えた分スペースを奪います。しかし電子の本・資料であればスペースは奪いません。
iPadの容量が超える場合はUSBに保存したり、電子書籍であれば購入した本を削除しても、購入データは残り続けるので再び読み直せます。もちろんその際にお金はかかりません。
2.半永久的に保管できる
紙は時が経つともろくなります。しかし電子書籍・資料は時間が経っても物理的に古くはなりません。自らデータを削除する、データが吹っ飛んでしまうといったことがない限りは一生残り続けます。
3.忘れない、失くさない
iPad内にたくさんの書籍やノートを保管できるため、1台のiPadを持っていけば「誤って違う書籍・ノートを持って行くこと」や「忘れたり、失くすこと」もありません。
4.誰にも見られない
日記やアイデア帳といった誰にも見られたくないノートや資料をiPadで作成しておけば、画面のロックができるので誰かに見られる心配もありません。
また電子書籍以外にも「耳で聴く本」の「オーディオブック」というサービスもあります。
耳で聴くだけで本の内容をインプットできるためオススメです。
オーディオブックに関する記事も投稿しているので、興味があれば読んでみてください。
家での趣味が増える、より楽しめる

不要なモノが減り、手軽になった分、自分の趣味に時間を費やせるようになりました。
最近ではコロナの影響でお家時間が増えました。そのため家でできる趣味を充実させたいと思った時に、iPadが活躍してくれました。
iPadには趣味という点で大きく2つのメリットが挙げられます。
- 画面がデカい
- マルチタスクできる
これらのメリットによって趣味がより楽しめるようになり、新しい趣味も増えました。
より楽しめるようになった趣味
- 動画鑑賞
- ゲーム
- 読書
iPadはこれらの趣味の充実度をあげてくれます。
画面が大きいので映画やドラマの迫力が増し、ゲームも操作がしやすくなり、読書であれば文字が読みやすいです。
また余談ですが、暗いところでも読みやすいので「寝る前に読書」ではなく「寝落ちするまで読書」も可能です。
新たに増えた趣味

- イラスト
- 動画編集
画面がでかいのでイラストを描くようになりました。
iPadは1画面で2つのアプリを同時に表示させ操作できます。
そのため、1画面内で参考にしたい絵を見ながら描くことができます
動画編集に関しても画面タッチを行いながら編集ができ、画面が大きい分スムーズかつストレスフリーで動画編集が行えています。
iPadの各最新モデル
| モデル | iPad (無印) | iPad Air | iPad Pro (11インチ) |
iPad Pro (12.9インチ) |
iPad mini |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新の世代 | 第9世代 | 第5世代 | 第3世代 | 第5世代 | 第6世代 |
| 見た目 |  |
 |
 |
 |
 |
| Apple pencil | 第1世代 | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 |
| Amazon | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る |
| 楽天 | 楽天市場で見る | 楽天市場で見る | 楽天市場で見る | 楽天市場で見る | 楽天市場で見る |
最後に
最後まで読んでいただきありがとうございます。
他にもまだiPadを使うことで今回紹介したこととは他の利便性や趣味などもあると思います。
iPadがあれば、趣味だけでなく副業や新たなビジネスにも繋がりやすいと思います。
それには行動・継続あるのみです!
また「【ミニマリスト】モノを減らすために 【買って良かったモノ】」という記事も投稿していて、こちらではiPad以外にもモノを減らしてくれるアイテムを紹介しています。
今後もミチバブログでは日々の生活がより楽に、より快適になるようなお役立ち情報を発信してきますので、ぜひまた読みにきてください。